
東北地域発ディープテックスタートアップのCXO候補募集プロジェクト
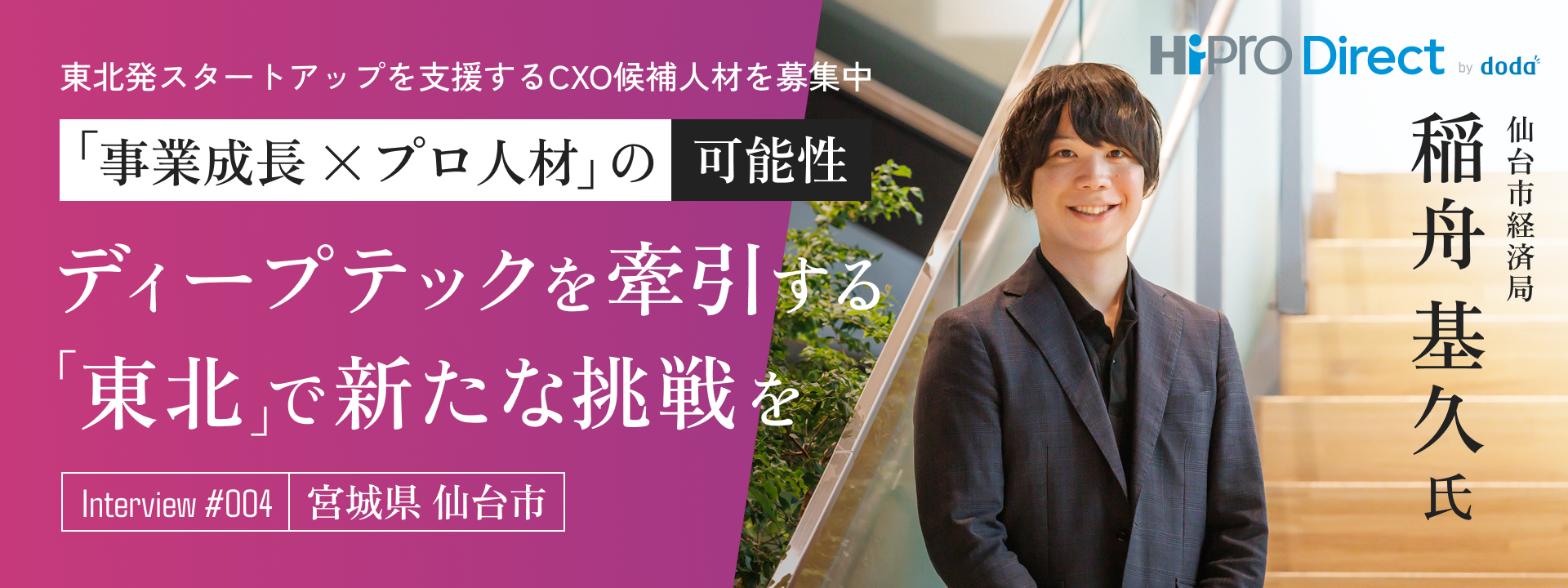
東日本大震災後、顕在化した社会課題を解決しようとソーシャルビジネスを立ち上げる人が増えています。特に仙台市は、2013年に「日本一起業しやすいまち」を目指す都市宣言を出し、以来、起業支援策を次々と打ち出してきました。 2023年には、「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」のプログラムを立ち上げ、東北のスタートアップ・エコシステムに首都圏の人材を流入させる基盤を構築。東北大学など、アカデミアで生まれているディープテックの研究シーズの事業化や、東北のスタートアップ支援が活発化しています。 こうした動きの背景や今後の展望について、仙台市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課の稲舟 基久さんにお話を伺いました。

仙台市経済局
イノベーション推進部スタートアップ支援課 稲舟 基久 氏
2019年から3年間、経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室でJ-Startupプログラムなどスタートアップ支援や、スタートアップ・エコシステムの構築に従事。2022年に仙台市に戻り現職に。「首都圏等スタートアップ支援構築事業」を担当し、東北のスタートアップへの成長支援に携わっている。
「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」の前身は、2022年度から立ち上がったプログラムで、当初は東北のスタートアップのエコシステムに首都圏の人材をつなげて、起業に関する情報格差を埋める目的でスタートしました。併せて、東北のスタートアップの首都圏への情報発信という意味合いもありました。
2023年度には「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」を立ち上げ、さらに内容を拡充しています。東北の大学に所属する研究者が持つ技術シーズの事業化や、スタートアップとしての成長が期待される個人や企業への伴走支援プログラムを本格的に展開しました。2023年、2024年度ともに約5社が採択され、1社あたり平均2名のCXO候補人材が伴走しました。
2025年度は、支援企業のレイヤーを一段階引き上げる予定です。たとえば、すでにシリーズAの資金調達を終えている東北大学発の有望なスタートアップに対して、将来的にフルコミットできる人材の募集も視野に入れた取り組みを進めています。このように「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」は、東北におけるスタートアップ・エコシステムの強化を目的とした、仙台独自の成長支援プログラムとして進化を続けています。

仙台市にとどまらず、東北6県のスタートアップと、首都圏等で活躍するCXO候補人材のマッチングを行っています。事業課題の解決に向けて、6か月間の伴走支援を実施しており、実践的なサポートを通じてスタートアップの成長を後押ししています。
スタートアップ各社とCXO候補人材が顔合わせするイベントも開催し、東北にゆかりのある人材や東北に興味を持つ人材と、スタートアップの方たちが広く交流できる場も設けます。タッチポイントを増やすことで、新たな人流を起こせればと考えています。

東日本大震災が契機になったことは確かです。震災によって地域の社会課題が顕在化し、課題を解決するために、多くの人が利他的な動機から起業に踏み出しました。2013年に「日本一起業しやすいまち」を宣言し、当初はスモールビジネスが中心でしたが、2014年から2016年には「政令指定都市の新規開業率」で全国2位(※)になるなど大きな動きがありました。
(※)出典:仙台市経済成長戦略2023(仙台市)
2017年からは、ディープテックスタートアップとソーシャルスタートアップそれぞれのアクセラレーションプログラムも走らせています。2025年には「グローバル拠点都市」に選定され、国際的な成果創出が期待されています。
東日本大震災を契機とした十数年にわたる取り組みの延長線上にあるのが、現在注力しているディープテックスタートアップへの支援です。2024年3月には待望の支援拠点「仙台スタートアップスタジオ」も開設されました。
「スタートアップスタジオ」では、仙台や東北の起業家はもちろん、首都圏で活動するスタートアップ経営者やベンチャーキャピタル(VC)、士業や専門家の方々も無料で相談できる体制が整っています。たとえば、資金調達を目指すスタートアップであれば、VCとのマッチングから、戦略の壁打ち、ピッチ資料のブラッシュアップまで、事業の成長フェーズに応じたきめ細かな支援を受けることが可能です。

はい。東北大学は、もともと学内に優れた技術シーズを数多く有しており、それらを事業化するための専門組織も整備されています。直近の例では、起業から数年で大きな成果を上げている医療系スタートアップも誕生しています。
さらに2024年には、東北大学が「国際卓越研究大学」に認定されました。「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」の立ち上げはこの認定よりも前のことですが、結果的に追い風が吹く形になっています。
国際卓越研究大学として東北大学は、今後ますます国際化を加速させていく見込みです。たとえば、2029年までに約500名の海外研究者を受け入れる計画を発表しており、すでに米国でリクルートキャラバンも実施しています。このような人的投資に加え、インキュベーション施設の増設も進められる予定です。
「仙台に来れば、自分のやりたい研究ができる」と、世界中の第一線で活躍する研究者が東北大学に集まる未来が見えてきました。国際的にもよりいっそう競争力の高い研究大学となり、優秀な学部生や院生がさらに集まることは間違いありません。そして、さまざまな研究シーズから、新しいスタートアップが生まれていく環境になると考えています。
東北のスタートアップは、首都圏のスタートアップと比べると、良くも悪くも慎重に進める傾向があります。そのため、事業を一気にスケールさせるには勢いや外部の視点が必要になる場面も多いと思います。
そこで重要になるのが、首都圏で活躍するCXO候補人材の方々との接点です。経験やネットワークを持つ人材とつながることで、スタートアップが新たな視点を得たり、事業成長を加速させたりするきっかけになると考えています。
まさに「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」は、そうしたつながりを生み出すプラットフォームです。私たちとしても、よりよいマッチングが生まれるよう、引き続き尽力していきたいと思います。

現在、ヒアリングしている中で特に求められているのは、COOやCFO人材です。実務を粘り強く遂行できる方、営業力に長けた方、資金調達の経験が豊富な方などです。スタートアップ側も、すでにさまざまな手段で人材確保に取り組んでおり、人材に対する解像度は高いと感じています。
とはいえ、必要な人材をピンポイントで見つけるのは簡単ではありません。仮に見つかっても、どうやって参画してもらうかは常に課題としてあります。そのため「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」では、スタートアップとCXO候補人材のマッチングやお互いの理解を深めるきっかけづくりを行っています。

首都圏で活躍しているCXO候補人材やVCの方々にとって、地方の大学の技術シーズやスタートアップ企業と出会うことは、簡単ではありません。どうしても閉鎖的になりやすく、現実的に接点が持ちづらいのが現状です。
その点、「TOHOKU STARTUPS POWER UP PROJECT」にて行うイベント等への参加を通して東北のスタートアップコミュニティへ参加いただくことで、東北のスタートアップのみならず、東北大学をはじめとする各大学や支援機関のネットワークにスムーズにアクセスできるようになります。東北各県にはまだ知られていない有望な技術シーズが眠っている可能性が高く、それらにいち早く関われることは、大きな魅力です。
また、東北のスタートアップ側も、事業を成功に導く高度なスキルと、粘り強く事業を推し進める意欲を持つ人材を必要としています。圧倒的な成長を目指したい方、自ら社会変革を起こしたい方にとって、東北のスタートアップは絶好の挑戦の場となるでしょう。
「東北は遠い」と感じる方もいるかもしれませんが、仙台は東京から新幹線でわずか90分程度の距離です。首都圏内の移動よりも早い場合すらあります。まずはぜひ一度、仙台を訪れて、東北のポテンシャルに触れてみてください。
私たちは、より多くの方が東北のスタートアップ・エコシステムとつながり、新たな人流や化学反応が生まれることを期待しています。
※ 所属・肩書および仕事内容は、取材当時のものです。