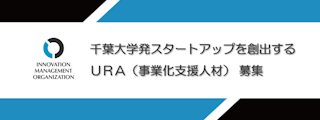
プロジェクト
千葉大学発スタートアップ創出を支援する、URA(事業化支援人材) 募集

40万円/月〜

120時間/月〜4日/週〜

国立大学法人千葉大学

大学で生まれた研究成果を事業化し起業する「大学発スタートアップ」の市場が急速に成長を遂げています。かつては年間数十社に限られていた設立数も、イノベーションエコシステムの活性化に伴い、2014年以降は年間200〜300社(※)と大きく増加してきました。この劇的な変化は、大学の研究成果を社会実装する新たな潮流を象徴しています。 千葉大学学術研究・イノベーション推進機構(IMO)は、大学発スタートアップの発展をさらに加速させるキーパーソンとなる人材を募集しています。本インタビューでは、千葉大学のスタートアップ支援戦略の核心に迫り、どのような人材が今、イノベーションを牽引する組織に求められているのか、IMOスタートアップ・ラボ 部長の片桐 大輔さんに聞きました。また、片桐さんとともに支援に取り組む客員起業家(以下 EIR)の加藤 優一さん、イノベーション・マネジメント研究員(以下URA)の松永 博充さんからも実際の業務内容について伺います。 ※出典:経済産業省「令和5年度 大学発ベンチャー実態等調査」

IMOスタートアップ・ラボ 部長
片桐 大輔 氏
国立大学法人千葉大学大学院 国際学術研究院教授 兼IMOスタートアップ・ラボ 部長。同大学大学院で薬学博士号取得。(独)NEDOフェロー、大学発スタートアップの起業や経営、ベンチャーキャピタリストなど経て、2022年より千葉大学IMOに参画しIMOスタートアップ・ラボを設置。2024年より現職。第12回(平成26年度)産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞受賞。

客員起業家(EIR)
加藤 優一 氏
国立大学法人千葉大学IMOスタートアップ・ラボ 客員起業家(EIR)。メーカーでの研究開発、コンサルティングファームで新規事業創出のコンサルティングに従事。現在はスタートアップで事業開発活動をしながら、2024年よりIMOスタートアップ・ラボにEIRとして参画。

イノベーション・マネジメント研究員(URA)
松永 博充 氏
国立大学法人千葉大学IMOスタートアップ・ラボ イノベーション・マネジメント研究員(URA)。総合電機メーカーにて国内原子力発電所のマネジメント業務および基礎研究センターでの環境系事業開発に従事。現在は、独立行政法人にて日本のSociety 5.0を実現するためのアーキテクチャ支援を行う傍ら、2024年よりIMOスタートアップ・ラボにURAとして参画。

片桐氏:この組織が立ち上がったのは、2022年です。大学の研究者が取り組んでいる研究シーズを事業化する、学生たちがつくるスタートアップを支援する組織です。……と、このように言うのは簡単なのですが、実現していくのは非常に難しい。この取り組みを一緒に支援してくださる人材を探すため、HiPro DirectにてEIR、URAの募集を行っています。
最初は兼務、つまりは副業や兼業として携わっていただいて構いません。このインタビューに同席している加藤や松永も副業でジョインしてくれています。支援人材のみならず、将来的にスタートアップの経営に携わりたい方も歓迎します。
片桐氏:千葉大学は、大学院生と学部生を合わせて1万3,000人、教員は1,500人ほどいる総合大学です。にもかかわらず、当大学から生まれるスタートアップの数は年間0〜2件と非常に少なく、課題となっていました。
私たちは必ずしも数にこだわっているわけではありませんが、とはいえ、所属している人数に比べて少なすぎる印象です。他の進んでいる大学に遅れを取っている点であり、千葉大学の理念である「つねに、より高きものをめざす」ために克服するべきだと考えます。
片桐氏:おっしゃる通りです。現在は、スタートアップや研究成果の事業化について、大学全体の機運を高めていく必要がある段階です。しかしこの時、無理に起業を煽ってただ起業数が増えればよい、とならないように注意しなければなりません。
私たちが国立大学としての使命をよく考え、研究成果を活用することで、社会課題解決に資する起業を本気で応援していくことが重要だと思います。国立大学の活動資金の原資の多くは税金です。多くの税金を投入してきた研究成果を社会に還元し、スタートアップ等を含めたエコシステムの中で成長させ、その成果をまた、研究へ還元していく。そうした、イノベーションエコシステムの形成を目指して、日々、取り組んでいます。
IMOスタートアップ・ラボでは次の三つを常に心掛けながら、スタートアップ支援を行っています。一つ目は「研究成果の社会実装を幅広に検討する」、二つ目は「社会課題を適切に捉えバックキャストして研究成果の活用を考える」、三つ目は「研究者や学生が起業したいと思ったときに、気軽にアクセスできる環境づくりを行う」です。

加藤氏:私はメーカーでエンジニアとしてはたらき、その後はコンサルティングファームで技術をベースにした新規事業創出の支援を行いました。現在はスタートアップで事業開発の仕事をしながら、IMOスタートアップ・ラボでEIRをしています。こういったバックグラウンドがあるため、研究で生まれた技術から新しいビジネスを生み出すことに強い関心を持っていました。そこで、IMOスタートアップ・ラボのEIRに応募したのです。
EIRとしては、千葉大学の持つ技術を俯瞰して見る、その上で各先生に詳しい話を聞きに行くことから仕事が始まります。事業化フェーズまで考えている先生もいれば、技術の探求に重きを置く先生もいらっしゃいます。いずれの先生でも、優れた技術を事業として社会に還元するために、アイデアを膨らませることが大切なポイントです。
松永氏:私はかつて総合電機メーカーで原子力発電所のマネジメントや基礎研究の事業開発を行っていました。その後、独立行政法人に転職し、日本のSociety5.0(サイバー空間と現実空間を融合することで、経済発展と社会課題解決を両立する社会)実現に向けたデジタルアーキテクチャ支援を行っています。独立行政法人の仕事に、現在面白さを感じながら取り組んでいる一方、これまでのキャリアを活かしながら、世の中のためになる新しいものを生み出したい、と思っていたところに出会ったのがIMOスタートアップ・ラボの人材募集でした。
つまり私も加藤と同じように副業でURAを務めています。IMOスタートアップ・ラボのURAには大きく3つの業務があります。一つ目は「学内の起業につながる可能性のある研究シーズの発掘」、二つ目は「先生や客員起業家の伴走支援」、三つ目は「学生向けアントレ教育」となり、私は一つ目と二つ目の業務に携わっています。業務にあたってはどのような技術を研究されているのか、先生から直接話を伺うことを大切にしています。それに加えて、EIRである加藤への伴走支援も大切な仕事です。
松永氏:そうですね。たとえば私は1,500人の先生がどのような研究をしているかをリスト化しています。それを加藤と共有し、関心を持った研究室を訪問する、ということをしています。先生方との信頼を築くためには「会いに行って話を聞く」という“ドアノック力”も必要だと思います。
片桐氏:EIRが出した起業アイデアをURAが壁打ちしたりもしています。既にお二人とも能力が高いため、壁打ちというより、噛み合った双方向のディスカッションになっており、理想的な関係だと思います。

松永氏:千葉大学には、多種多様で先進的な研究シーズが多く存在し、さまざまな社会課題の解決に寄与する可能性を秘めています。しかし、どれほど優れた研究成果であっても、市場のニーズに直結するわけではありません。
これらの研究成果を社会実装し、課題解決に結びつけるためには、産学連携が不可欠であり、明確な道筋の構築が求められます。その仕組みづくりを私たちURAが担っており、「技術を課題解決につなげられる」というのがやりがいの一つです。
また、私自身は次の世代への引き継ぎを考える年齢になりました。IMOスタートアップ・ラボの仕事を通じて、次の世代に素晴らしい技術やプロダクト、そして“未来の地球”を引き継いでいければと思います。
加藤氏:私も社会課題解決が一番のやりがいではないかと考えています。「技術は何のためにある?」と考えると、「使うためにある」というのが私のスタンスです。技術を進化させることはとても重要ですが、それだけがゴールではなく、どう使うか、つまり社会実装につなげていくことにやりがいを感じます。
世の中の社会課題を捉え、どの技術で解決していくかを考えることが、この仕事の面白さだと思います。

片桐氏:まず、加藤や松永のように副業として来ていただいてまったく問題ありません。むしろ、副業や兼業の方は意欲や能動的に動く力が高いと思うようになりました。
千葉大学のスタートアップ支援は他大学に比べるとまだまだ克服すべき課題が多い状況です。だからこそご自身でアイデアを出し、それを形にしやすい環境であると言えます。はたらく方の経験やスキルアップにつながる組織だと自負しています。
スタートアップ、起業は単なるお金を稼ぐ手段ではなく、大企業も解決できない課題を独自のアイデアでブレークスルーする存在、方法として期待されています。だからこそ、学界はもちろん、既存企業や行政も支援をしているのです。世の中をよりよい方向へ動かしたいと考える技術者やビジネスパーソンにとって、社会貢献の実感をスタートアップ支援の現場で得ることができるかもしれません。
千葉大学発のスタートアップ創出に携わるチャンスに、ぜひチャレンジしてみてください。

※ 所属・肩書および仕事内容は、取材当時のものです。